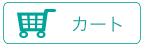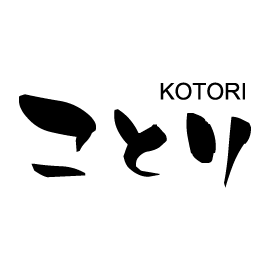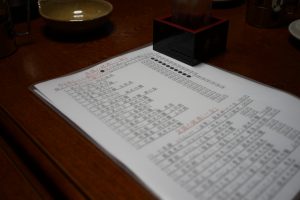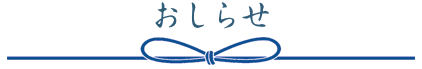5月2日以降の営業日について
ゴールデンウィーク及び5月6日以降の営業日をお知らせ致します。
5月2日(火)〜5日(金):出荷業務停止、お電話及びメールでのお問い合わせのみとなります。
5月6日(土)〜14日(日):お休み、メールでのお問い合わせのみ受け付けておりますが、お返事までお時間を頂く場合がございます。
5月15日(月)以降:営業日が変更になります。土日祝日がお休みとなりますが、営業時間に変更はございません。
ゴールデンウィーク中の納期に関して
端午の節句まで日がなくなってまいりましたので、今後の出荷予定日とお届け予定日をお知らせ致します。
本日から5月1日お昼12時までのご注文分に関しましては、全て5月1日出荷となります。
大変申し訳ございませんが、5月5日までにお届け出来ますのは上記までとなります。
ご注文日:4/29(土)〜5/1(月)お昼12時
↓
最短お届け日:5月2日(火) 〔北海道、九州、四国の一部は+1日〕
※なお、ご注文フォーム上では上記のお届け日がご指定頂けないため、備考欄にご希望のお日にちとお時間をご記載下さい。
※キャンペーンの名入れ木札につきましては、制作時間の都合上5月5日以降に別便にてお届けとなります。
特にお急ぎの場合は電話かメールでお問い合わせください。少しでも早くにお客様のお手元にお届け出来るよう対応させていただきます。
フリーダイヤル:0120-303-773
お問い合わせ
関東では桜のピークも終わり、暖かい日が続くようになりました。来週末からゴールデンウィークという方もいらっしゃるのではないでしょうか。端午の節句ももうすぐそこですね。「ことり」でもお届け日に関するお問い合わせを多数頂くようになりましたので、お知らせにお届け迄の日数短縮の案内を掲載致しました。ご注文の際に、お急ぎの旨をお伝え頂きましたら出来る限り対応いたします。

新暦の端午の節句は5月5日こどもの日ですね。そろそろ鯉のぼりが上がっているのを見かけるようになりました。最近は集合住宅ですとベランダに鯉のぼりが出せないところもあるようで、昔ほどたくさん鯉のぼりは見かけなくなってきています。「ことり」では兜と一緒に飾っていただける室内鯉飾りを用意しています。ぬいぐるみタイプの可愛い室内鯉飾りです。気になる方はリンクから商品をご覧ください。
ゴールデンウィーク中は全国で鯉のぼりイベントを開催しているようです。自宅では大きい鯉のぼりはちょっと無理という方も大きい鯉のぼりが空を泳いでいるのを満喫出来ますよ。

最近では新暦でお祝いする地域が多いと思いますが、節句はもともと旧暦に合わせて作られました。端午の節句に欠かせない菖蒲も新暦の5月5日にはまだちょっと時期が早いですが、今年の旧暦の端午の節句である5月30日には見頃を迎えます。

ちょうどこの時期になると気温もだいぶ暖かくなり、梅雨に突入。昔は食べ物も痛みやすく、子供が体調を崩したり、怪我が悪化したりすることも多かったでしょう。特に小さい子供には注意が必要だったと思います。
ですからこの時期に子供の健康を祈願する端午の節句をお祝いし、邪気を祓うことが大切だったのかもしれません。新暦でお祝いされる地域であっても、旧暦の節句まで兜を飾ってもう少しゆっくりお祝いすることで、また違った気持ちで節句を迎えることが出来るかもしれないですよ。
「ことり」では引き続き旧暦の端午の節句まで。兜の販売をしております。

端午の節句も近づいてまいりましたので、お届けまでを4営業日以内(北海道、九州、四国は5営業日以内)と短縮いたしました。例:4月22日ご注文の場合、4月26日お届け
特にお急ぎの場合は電話かメールでお問い合わせください。少しでも早くにお客様のお手元にお届け出来るよう対応させていただきます。
フリーダイヤル:0120-303-773
お問い合わせ
鷹シリーズから「要」を紹介します。


全体的に赤と黒のコントラストが大変美しい兜収納セットです。「要」のポイントは大変目を引く赤い印伝吹返しと赤い忍緒。とても堂々として美しい兜です。後ろ姿は人気のある一番上が白で下が赤い縅しです。吹返しには魔除けの菱菊紋が描かれています。

飾台と屏風には「鼓」が描かれていますが、実は鼓は昔から武士に愛された楽器でした。鼓が重要な役割を占める能は織田信長をはじめとする多くの武将に愛され、江戸時代には式楽となります。徳川家光の時代には能は武士が正しい発音、豊な声量、優雅な身のこなしを身につけるために用いられ、「見て楽しむ芸」から武士・支配階級が鼓を打たせて「自ら演じて楽しむ芸」になっていきます。
気力、体力共に要求される能は「気合の芸術」とも言われる力強い芸能であり、直線的に気持ちよく破裂音が抜けていく鼓の音は武家の気質に合ったものだったのでしょう。上級武士は、戦に向かう前に不安や緊張を力に変える為に舞うこともあったそうです。そこから転じて今でも邪気を祓う雅な音として、豊かさを表す吉祥文様として定着したのでしょう。

いつも会津若松に行くと日本酒を買って帰るのですが、今回は仕事終わりが遅く日本酒を買うことが出来ませんでした。酒造さんは閉まるのが早く残念です。ですが、「舞酒」という地元のお酒を揃えているお店へ連れて行ってもらいました。野菜も美味しかったのですが、一番感動したのは桜レバーでした。初めて馬のレバーを食べましたが、プリプリで甘くてじんわり心に染みる美味しさです。地元でも食べられるお店がないか探してみます。

日本酒はスッキリしたものから主張のある物まで色々ありました。利き酒セットもあるので色々な種類を飲みたくても大丈夫。そんなに種類は飲んでいませんが、純米吟醸生原酒「末広」が良かったです。やはり口の中に長く余韻が残るお酒は飲んでいて楽しく感じますよね。また会津に来たら美味しい土地の物に出会いたいです。
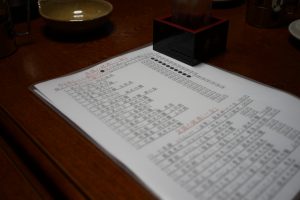
ちなみに前にブログに書いた太郎焼総本舗には間に合いました。工房スタッフがサリーちゃんを抱っこして幸せそうだったのが羨ましかったですが、私ももちろん遊んでもらいました。いつもいい子です。


定番の太郎焼きはお土産にして、今回は黒蜜きなこサンデーを注文。写真では分かりづらいですが、結構なボリュームです。他のスタッフは注文してからクリームを入れてくれるシュークリームに感動していましたが、このサンデーもリピート確実な美味しさでした。

気が早いようですが、来年の五月人形準備
先日来年販売する「ことり」の五月人形の準備をするために会津若松市へ行ってきました。今年の五月人形を販売中ですが、お客様のお声や店舗のスタッフの意見などを参考にしながらどういうものを作るのかの打ち合わせです。今年から始めた小さいサイズの雀シリーズが好評なのでこのあたりも充実させていきたいです。

色々な構想は練ってきたのですが、まだ形にはなっていないので写真でお見せ出来ないのが残念です。代わりに漆器屋さんで見つけた素敵な重箱の写真を紹介します。色や構図も素敵ですが何と言っても盛上の迫力が凄いです。その中にも繊細な描き込みがされていてずっと見ていられそうです。


さりげなく螺鈿細工(漆塗りの表面を彫り込み、そこに貝片をはめ込む細工)も施されています。こんなのが家にあったら素敵だなと思いながら値段を確認してみたら25万円。写真だけ撮らせていただいてそっとショーケースの中に戻しました。

この週末、関東地方はちょうど桜が満開なのでお花見している方も多いのではないでしょうか。仕事柄なかなかゆっくりお花見が出来ないのですが、素敵な桜の蒔絵の入った漆器でお花見気分も味わえました。

「ことり」では昔ながらのオーソドックスな金兜の他に徳川家康と伊達政宗の兜を取り扱っていますので、この二人の武将を簡単に紹介したいと思います。

「徳川家康」泰平の世を築いた天下取りの兜
徳川家康という武将は天下統一、戦のない世の中を作った人というイメージが強いかと思います。徳川家康について簡単に調べてみると他の武将に比べて健康、人間関係、財産に恵まれ享年75歳という当時としてはとても長寿な方でした。こう聞くと凄く順調な人生を歩んでいたように見えてしまいますが、決して順風満帆と言うわけではなく、幼少から人質に取られ、実父は若くして亡くなるなど逆境にいながら自分で運命を切り開いていく力のあった方だったようです。大変強運の持ち主でもあったと言われていますが、きっとチャンスが巡ってきた時に逃さないよう普段から準備してきたのだと思います。大変勉強家だったそうですが、回りにいる優秀な武将と関わる中で最善策が打てるように大局観も幼い頃から磨いてきたのかもしれません。

「伊達政宗」連戦連勝の勝ち兜
伊達政宗のイメージは戦に負けない強い武将ではないでしょうか。
伊達政宗は17歳で家督を継ぎますが、なんとその翌年には軍事行動開始しています。最初は大きな戦ではなく内輪揉めを治めたところから始まり、その後領土拡大の為に戦い22歳にして伊達氏の最大勢力を築いたそうです。これをみるとまさに猛将に見えますが、外交や政略に優れ敵を弱体化させた後そこから勝利を得る智将だったようです。戦だけではなく自領の発展に尽くしたり海外へ家臣を派遣するなど広い視野を持ち合わせた武将でした。教養人としても知られ、天皇より和歌を称賛されたり能へ傾倒するなど文武両道も高く評価されていました。晩年は戦国の雄として徳川家光から尊敬をうけ、70という長寿を全うしました。
なんとなくデザインで選びがちな兜飾りですが、自分が気に入った兜の持ち主がどんな人だったのかを調べてみるのも楽しいですよ。お子様が大きくなられた時にお話してあげるとより一層愛着も湧いてくるかもしれませんね。

大切なお子さまを大人になるまで見守る、五月人形。そんな大切な存在だから、ホームページのお写真だけではなく、やはり実物を見てみたいという声をよく伺います。
当店では直営店「人形の甲州屋」を3店舗運営しております。
多数の「工房ことり」の商品だけでなく、全国各地の著名作家や鎧飾り、ケース飾りなども多数取り揃えております。また、鯉のぼりも各種取り扱っております。
お近くの方は是非ともご来店頂けましたら幸いです。
直営店舗ご案内ページ
※109町田店では一部お取り扱いのない商品が御座います。