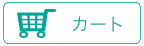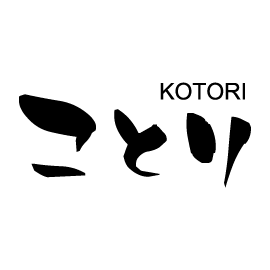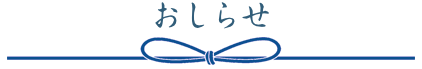五月人形ホームページリニューアルオープンのお知らせ
今年も新作の五月人形が出来上がりました。去年は初年度ということもあり、伝統的な色の組み合わせを多くご用意しておりましたが、意外にもアイボリーを基調とした兜収納飾りに人気が集中し、早い時期に完売となってしまいました。今年は好評だったアイボリーを使ったデザインを増やし、可能な限りお客様に一番欲しいと思っていただいた五月人形をお届け出来るようにしました。
新作のデザインも「ことり」らしく伝統文様を使いながらも、親しみやすく、色々なお部屋に馴染むような五月人形に仕上げました。兜の大きさも去年と同じ飾る場所を選ばないコンパクトサイズの飾り幅30cmと堂々とした大きさの飾り幅40cmをご用意しております。
ホームページリニューアルオープンは三月の上旬を予定しておりますが、まだ少し先なので、先にブログの方で商品をご紹介していきたいと思います。(先日の商品写真撮影中の写真、後日綺麗な写真をアップします)


ことり型名入れ木札 プレゼントキャンペーン
 昨年オープン記念で開催致しました「ことり型名入れ木札 プレゼントキャンペーン」は、非常にご好評を頂きました。
昨年オープン記念で開催致しました「ことり型名入れ木札 プレゼントキャンペーン」は、非常にご好評を頂きました。
今年は販売商品として検討しましたが、また今年も多数のお問い合わせを頂いておりますし、素敵なご縁を沢山いただいているので、
今年もまたプレゼントすることに決定しました!!
3月3日までにホームページにて雛人形セットをご購入頂きましたお客様、全てにプレゼント致します。
ご購入の際、備考欄にお子さまの生年月日とお名前をご記入ください。
なお、4文字以上になりますと文字が小さくなってしまいますので、フルネームではなくお名前のみのご記入をオススメしております。
更に今回は昨年の12月から今までに雛人形セットをご購入頂いた方にも、プレゼント致します。
ご購入済のお客様にはすでにキャンペーンのご案内のメールを送付しておりますが、万が一届いていないようでしたら、大変お手数ですが当店までメールもしくはお電話にてご連絡下さい。
※制作に約2週間程度かかる為、雛人形セットとお届け日が異なる場合もございます。
今回もことりのおひな様から一部ピックアップ商品を紹介いたします。

氷花(4H124A)
梅の花は百花に先かけて咲く花といわれ、寒い冬をじっと耐え春の訪れを知らせてくれる喜びの象徴とされてきました。更にその寒さの中、気高い香りと共に花を咲かせる生命力の強さから「高貴」「長寿」などと結びついて縁起の良い花となったと言われています。この気高く強く美しい梅を主題にしたおひな様です。




姫は雲立涌の織柄のある鮮やかな赤。殿にも威厳を感じさせる落ち着いた紺のお着物を着せ付けました。雲立涌は蒸気が立ち昇り、雲が沸き起る様子を象った文様です。雲気がゆらゆらと天に向かって湧きのぼるという壮大なイメージは、その雲が地上を覆い尽くすかの如く権力の象徴となったのでしょう。そのため古来より王朝貴族の衣裳に使われ吉祥的な意味合いとしてとても好まれてきたのかもしれなません。そしてそれぞれの着物には梅の花の刺繍を施しています。
高貴な色合いの殿姫の衣裳を引き立たせる為に、飾台は高級感のある黒と優しいアイボリーの二色の会津塗で仕上げ、明るい白和紙屏風に深紅の印象的な紅白梅を飾りました。春の香りまで運んでくるようなおひな様です。
ことりのおひな様から一部ピックアップ商品を紹介いたします。

星明かり(4H102)
シンプルながら可愛らしさ溢れるおひな様です。お人形の着物も飾台も控えめな色使いで厳しい寒さが緩み始める初春に、春の兆しをそこかしこに感じ喜びを見出すような雰囲気を楽しんでいただけるようにセットいたしました。




姫は淡いピンクに薄朱やクリーム、薄緑の小花が一面に広がる連続柄のお着物です。殿は姫とは色違いの共柄で、姫の淡いピンクと相性のよい薄紫にしました。連続柄には無限に広がっていく様子から、将来への展望、繁栄と言った意味が込められています。古くから使われてきた古典吉祥柄は長い時間をかけ洗練され、私達の生活の中に定着してきました。上品で可憐な衣裳を着たおひな様は飽きることなく、末永くお楽しみいただけると思います。


優しい色合いのおひな様の衣裳を引き立たせる為に、飾台は会津塗で優しいアイボリーに仕上げ、全体の雰囲気を壊さないように同じ色合いの和紙の屏風を合わせました。そこにアクセントとして上品なしだれ紅白梅を屏風に垂らして、華やかさをプラスしました。お部屋に飾っていただくとお部屋の雰囲気も明るくなるようなお飾りです。
スマートフォンサイトの最適化
12月後半に当店ホームページをスマートフォンに最適化する変更を行いました。
今まで以上におひな様をお選び頂きやすくなりました。
年明け早々ではありますが、当店でも完売のおひな様が出てきておりますので、気になるおひな様がありましたらお早めのご購入をお勧め致します。
些細なことでも質問や疑問などがございましたら、メールもしくはフリーダイヤルへお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
新年あけましておめでとうございます。
年末から年始にかけて多数のお問い合わせを頂き、有り難うございます。
人形工房ことりスタッフ一同、お客様方との素敵なご縁を沢山いただけるよう、頑張ってまいります。
本年もご愛顧の程宜しくお願い致します。

※写真はスタッフKが年始に山中湖付近から撮影したダイヤモンド富士です。
少し遅れておりましたが、ようやく今年の新作雛人形の準備が整いましたので、本日より販売を開始させていただきます。去年から引き続きで販売しているおひな様もありますが、お客様の声を参考に今年は大幅に新作を増やしました。一人に一つだけのおひな様。だから全てのおひな様に色々な願いを込めて丁寧に作りました。今年もお客様との素敵な御縁があると嬉しいです。


京唐紙屏風を合わせたおひな様2
前回に引き続き京唐紙屏風と合わせたおひな様のセットを紹介致します。派手目なつぼつぼ柄の物を紹介したので、今回は同系色でまとめた繊細な枝桜文様の屏風の物をピックアップいたします。

間口45cmの小さい方の枝桜柄の屏風は、落ち着いた会津塗で黒に仕上げた飾台と合わせました。淡いピンクに銀雲母と呼ばれるキラキラ輝く鉱石をまぜた絵の具を使用した唐紙は見る角度や光の当り方によって表情が変わります。光が弱く反射の少ない状態だとはっきりと柄が主張し、明るいお部屋では絵の具が桜色の和紙に溶け込むように見えます。


このセットに合わせた雛人形は殿と姫両方が、前回も紹介した麹塵(きくじん)の着物をきています。ただしこちらは紫に染めた麹塵で、光があたった時の色の変化は少ないですが、光があたると色が明るくなり赤みがより一層強くなるのをお楽しみいただけます。

裁断してしまう前の生地です。ただの紫に見えますが、鳳凰や亀、松、菊、竹、桐などめでたいしるしがふんだんに織り込まれています。とても細い糸で織られているので手触りは滑らかで光沢も美しいお着物です。

間口が52cm少し大きめの枝桜柄の屏風には、アイボリーに黒を重ねたシンプルながら綺麗な色の組み合わせを楽しめる会津塗の飾台を合わせました。


殿は紫、姫には魔除けの意味のある赤の着物を着せ付けました。そして殿姫共にお揃の宝尽くしの刺繍を施しています。宝尽くしとは吉祥文様の一つで、名前の通り宝物を集めた絵柄です。昔の柄なので不思議な宝物がたくさんあります。

隠れ蓑、隠れ笠・・・危険なものから自分の身を隠してくれる
宝珠、打ち出の小槌・・・願いを叶えてくれる
宝袋、宝鍵・・・金銀財宝が手に入る
巻物、軍配・・・知恵がつき商才が身につく
丁子・・・健康、夫婦円満
一つでも手に入ったらとても嬉しくなりそうな不思議道具の数々です。お子様に沢山の福をもたらすようにとこの刺繍を選びました。お子様が大きくなったときに、何気ない装飾にどんな思いが込められているのか、是非伝えていただけたらうれしいです。
京唐紙屏風を合わせたおひな様 1
前回京唐紙の紹介をしたので、今回は京唐紙屏風と合わせたおひな様のセットを紹介致します。
今回は平飾りのみで、間口45cmと52cmの二種類のラインナップをご用意しました。
屏風にこだわったので、それに合わせてお人形の衣裳もお道具もグレードの高いものを合わせました。あまりお人形には使われない珍しい衣裳も取り入れました。

間口45cmの小さい方のつぼつぼ柄の屏風は、落ち着いた会津塗で朱色に仕上げた飾台と合わせました。おひな様は屏風のインパクトに負けない鮮やかな色の衣裳を着せ付けました。この生地は人が着るお着物の帯用にデザインされているものを、あえて小さいお人形に使っています。その為、着物の柄全体は分かりにくいのですが、帯地ならではの繊細な色の出方をお楽しみいただけます。鮮やかな黄色の中に繊細な紫、溶け込むように馴染んだ緑や青の色味がご覧いただけます。

前のブログでも紹介しましたが、裁断してしまう前はこんな帯でした。目を引く美しい帯ですよね。お道具もこのおひな様に合わせて金箔を使用した贅沢な物を用意しました。

間口が52cm少し大きめのつぼつぼ柄の屏風には、黒に朱色を重ねたシンプルながら綺麗な色の組み合わせを楽しめる会津塗の飾台を合わせました。殿の衣裳は拡大して見ていただくと、紫色と緑が混じったような色に見えているのでは思います。実は殿衣裳は一般家庭の蛍光灯の下で見ると落ち着いた深い緑色なのですが、殿の衣裳が麹塵(きくじん)という特別な染め方をした生地なので、光の当たり方で色が変化するのです。

古来は天皇のみが着ることの出来る「禁色」でした。他の染物では考えられないほどの種類の染料を使い、とても手間がかかる工程を経て染められるそうです。職人の方の努力の末、照らされる光の違いで、深い緑から赤紫まで色を変える不思議な反物が誕生します。緑の生地が明るい昼の太陽に照らされて赤く輝く様子は本当に綺麗です。(おひな様は直射日光厳禁ですが)

姫は殿と合わせた格調高い着物にしました。平安以降公家階級が身につけた有職文様の一つ、菊は不老長寿を表すめでたいしるしとして好まれてきました。殿姫ともに晴れのお祝いの席にピッタリの衣裳を着たセットになりました。
日本には職人さんが手間暇を惜しまずに作った素敵なものがたくさんあります。雛人形も沢山の職人さんが関わることによって出来ています。着物の生地を織ってくれる織工さんや、お人形の頭を作ってくれる頭師さん、雛小道具や飾台を作ってくれる職人さん。誰が欠けても素敵な雛人形を作ることが出来ません。


「ことり」では雛人形の飾台や屏風に会津若松の伝統工芸品である会津塗で仕上げていますが、他にも取り入れていきたい工芸品が沢山あります。そのうちの一つが京からかみです。
時々目にする京唐紙が素敵で、旅館やホテルなどさり気なく使われているのを見るたびに、おひな様の屏風にしたら素敵だろうなと思っていました。今までは製作の過程で難しい部分があって断念していたのですが、解決策が見つかり今年は素敵な屏風を作ることが出来ました。
京唐紙は簡単に言うと版画のような製造工程で作られています
1:木製の版木を作る
2:顔料や鉱石、布海苔などを混ぜて好みの絵の具を作る
3:篩(ふるい)と呼ばれる丸い枠に布を張ったものに絵の具を塗る
4:3を版木に何度か軽く押し当て色を乗せる
5:紙を版木に押し当て、均等に絵柄が紙に写ったら乾かして完成
オリジナル屏風製作の打ち合わせの写真を撮ってくるのを忘れてしまい、準備の様子をお伝え出来ないのですが、色々教えて頂きとても勉強になりました。色とりどりの和紙に無数にある摺り色、そして文様。どの組み合わせにするかかなり難しかったのですが、アドバイスをいただき全くタイプの違うもの三種類を用意することが出来ました。

紗綾・・・武家好みと言われる文様の一つ。格調の高さを表現した幾何学文様

枝桜・・・町家好みと言われる文様の一つ。柔らかい曲線の中にたくましく生きる心意気を表現

つぼつぼ・・・茶方好みと言われる文様の一つ。“わび”という美の感覚を追求した洗練されたデザイン。通常一色で摺るのですが、今回は二色にしてもらいポップに仕上げました。
次回は京唐紙を使ったおひな様のセットを紹介したいと思います。