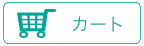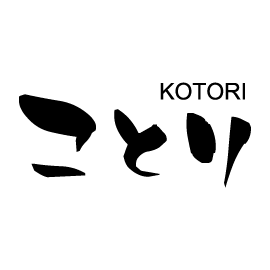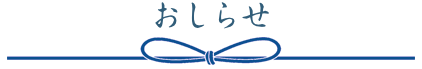日本には職人さんが手間暇を惜しまずに作った素敵なものがたくさんあります。雛人形も沢山の職人さんが関わることによって出来ています。着物の生地を織ってくれる織工さんや、お人形の頭を作ってくれる頭師さん、雛小道具や飾台を作ってくれる職人さん。誰が欠けても素敵な雛人形を作ることが出来ません。
「ことり」では雛人形の飾台や屏風に会津若松の伝統工芸品である会津塗で仕上げていますが、他にも取り入れていきたい工芸品が沢山あります。そのうちの一つが京からかみです。
時々目にする京唐紙が素敵で、旅館やホテルなどさり気なく使われているのを見るたびに、おひな様の屏風にしたら素敵だろうなと思っていました。今までは製作の過程で難しい部分があって断念していたのですが、解決策が見つかり今年は素敵な屏風を作ることが出来ました。
京唐紙は簡単に言うと版画のような製造工程で作られています
1:木製の版木を作る
2:顔料や鉱石、布海苔などを混ぜて好みの絵の具を作る
3:篩(ふるい)と呼ばれる丸い枠に布を張ったものに絵の具を塗る
4:3を版木に何度か軽く押し当て色を乗せる
5:紙を版木に押し当て、均等に絵柄が紙に写ったら乾かして完成
オリジナル屏風製作の打ち合わせの写真を撮ってくるのを忘れてしまい、準備の様子をお伝え出来ないのですが、色々教えて頂きとても勉強になりました。色とりどりの和紙に無数にある摺り色、そして文様。どの組み合わせにするかかなり難しかったのですが、アドバイスをいただき全くタイプの違うもの三種類を用意することが出来ました。
紗綾・・・武家好みと言われる文様の一つ。格調の高さを表現した幾何学文様
枝桜・・・町家好みと言われる文様の一つ。柔らかい曲線の中にたくましく生きる心意気を表現
つぼつぼ・・・茶方好みと言われる文様の一つ。“わび”という美の感覚を追求した洗練されたデザイン。通常一色で摺るのですが、今回は二色にしてもらいポップに仕上げました。
次回は京唐紙を使ったおひな様のセットを紹介したいと思います。