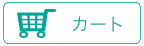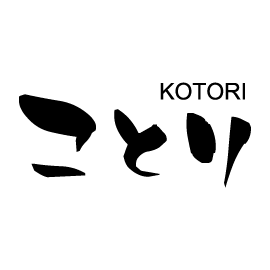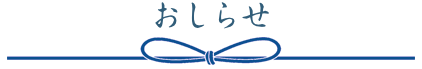前回に引き続き京唐紙屏風と合わせたおひな様のセットを紹介致します。派手目なつぼつぼ柄の物を紹介したので、今回は同系色でまとめた繊細な枝桜文様の屏風の物をピックアップいたします。
間口45cmの小さい方の枝桜柄の屏風は、落ち着いた会津塗で黒に仕上げた飾台と合わせました。淡いピンクに銀雲母と呼ばれるキラキラ輝く鉱石をまぜた絵の具を使用した唐紙は見る角度や光の当り方によって表情が変わります。光が弱く反射の少ない状態だとはっきりと柄が主張し、明るいお部屋では絵の具が桜色の和紙に溶け込むように見えます。
このセットに合わせた雛人形は殿と姫両方が、前回も紹介した麹塵(きくじん)の着物をきています。ただしこちらは紫に染めた麹塵で、光があたった時の色の変化は少ないですが、光があたると色が明るくなり赤みがより一層強くなるのをお楽しみいただけます。
裁断してしまう前の生地です。ただの紫に見えますが、鳳凰や亀、松、菊、竹、桐などめでたいしるしがふんだんに織り込まれています。とても細い糸で織られているので手触りは滑らかで光沢も美しいお着物です。
間口が52cm少し大きめの枝桜柄の屏風には、アイボリーに黒を重ねたシンプルながら綺麗な色の組み合わせを楽しめる会津塗の飾台を合わせました。
殿は紫、姫には魔除けの意味のある赤の着物を着せ付けました。そして殿姫共にお揃の宝尽くしの刺繍を施しています。宝尽くしとは吉祥文様の一つで、名前の通り宝物を集めた絵柄です。昔の柄なので不思議な宝物がたくさんあります。
隠れ蓑、隠れ笠・・・危険なものから自分の身を隠してくれる
宝珠、打ち出の小槌・・・願いを叶えてくれる
宝袋、宝鍵・・・金銀財宝が手に入る
巻物、軍配・・・知恵がつき商才が身につく
丁子・・・健康、夫婦円満
一つでも手に入ったらとても嬉しくなりそうな不思議道具の数々です。お子様に沢山の福をもたらすようにとこの刺繍を選びました。お子様が大きくなったときに、何気ない装飾にどんな思いが込められているのか、是非伝えていただけたらうれしいです。