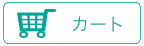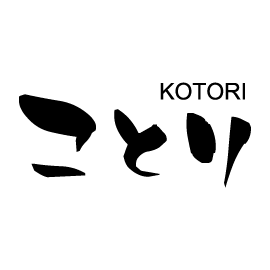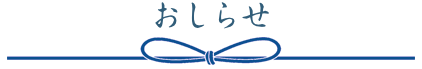前回京唐紙の紹介をしたので、今回は京唐紙屏風と合わせたおひな様のセットを紹介致します。
今回は平飾りのみで、間口45cmと52cmの二種類のラインナップをご用意しました。
屏風にこだわったので、それに合わせてお人形の衣裳もお道具もグレードの高いものを合わせました。あまりお人形には使われない珍しい衣裳も取り入れました。
間口45cmの小さい方のつぼつぼ柄の屏風は、落ち着いた会津塗で朱色に仕上げた飾台と合わせました。おひな様は屏風のインパクトに負けない鮮やかな色の衣裳を着せ付けました。この生地は人が着るお着物の帯用にデザインされているものを、あえて小さいお人形に使っています。その為、着物の柄全体は分かりにくいのですが、帯地ならではの繊細な色の出方をお楽しみいただけます。鮮やかな黄色の中に繊細な紫、溶け込むように馴染んだ緑や青の色味がご覧いただけます。
前のブログでも紹介しましたが、裁断してしまう前はこんな帯でした。目を引く美しい帯ですよね。お道具もこのおひな様に合わせて金箔を使用した贅沢な物を用意しました。
間口が52cm少し大きめのつぼつぼ柄の屏風には、黒に朱色を重ねたシンプルながら綺麗な色の組み合わせを楽しめる会津塗の飾台を合わせました。殿の衣裳は拡大して見ていただくと、紫色と緑が混じったような色に見えているのでは思います。実は殿衣裳は一般家庭の蛍光灯の下で見ると落ち着いた深い緑色なのですが、殿の衣裳が麹塵(きくじん)という特別な染め方をした生地なので、光の当たり方で色が変化するのです。
古来は天皇のみが着ることの出来る「禁色」でした。他の染物では考えられないほどの種類の染料を使い、とても手間がかかる工程を経て染められるそうです。職人の方の努力の末、照らされる光の違いで、深い緑から赤紫まで色を変える不思議な反物が誕生します。緑の生地が明るい昼の太陽に照らされて赤く輝く様子は本当に綺麗です。(おひな様は直射日光厳禁ですが)
姫は殿と合わせた格調高い着物にしました。平安以降公家階級が身につけた有職文様の一つ、菊は不老長寿を表すめでたいしるしとして好まれてきました。殿姫ともに晴れのお祝いの席にピッタリの衣裳を着たセットになりました。